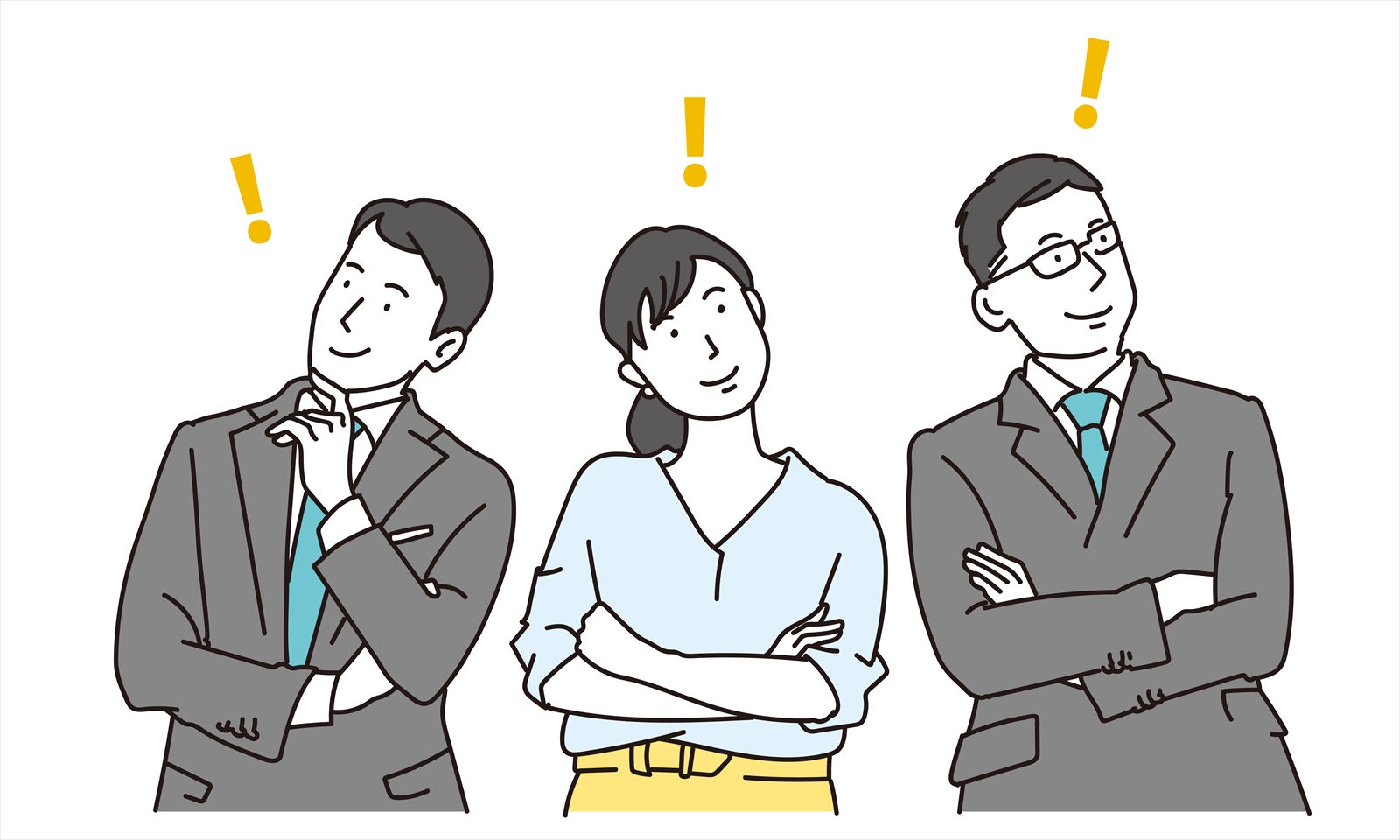採用活動を行う際、「従業員」という言葉を何気なく使っているかもしれません。しかし、正社員だけでなくアルバイトやパートも従業員に含まれるのかどうか、法律上の定義や従業員数の数え方、保険の加入などを正しく理解した上で、採用していくことが大切です。
この記事では「従業員」の定義から「社員」との違い、従業員に含まれる・含まれない雇用形態、従業員数の数え方、加入が必要な保険まで、人事・労務担当者や採用担当者が押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
目次
「従業員」の定義とは?
まずは、「従業員」という言葉が法律上どのように定義されているのか、また一般的にどのように使われているかについて解説します。
「従業員」とは、企業や団体に雇用され、労働契約に基づき労働を提供している人を指します。一般的には正社員、契約社員、アルバイト・パートタイマーなど、会社と直接雇用契約を結んでいる人が含まれます。
法律上の「労働者」ともほぼ重なる概念であり、労働基準法第9条では「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定められています。(出典:厚生労働省「労働者とは」)
「社員」との違いはある?
「従業員」と「社員」の違いはあるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
「社員」という言葉は、一般的には「正社員」の意味合いで使われることが多いですが、法律上は会社法における「社員(株主などの出資者)」を指す場合もあります。一方、「従業員」は雇用形態を問わず、会社と雇用契約を結び働いている人全体を指します。
つまり今回の場合、「社員」は「従業員」の一部に含まれると考えるのが一般的です。
従業員に含まれる代表的な雇用形態
では次に、従業員に含まれる代表的な雇用形態について、種類ごとに整理して解説します。
正社員
正社員は、期間の定めがない雇用契約を締結し、会社の中核を担う存在です。雇用契約においては定年までの長期雇用を前提とし、労働時間もフルタイムが基本です。社会保険(健康保険、厚生年金保険など)や雇用保険などにも原則として加入します。
契約社員
契約社員は、一定期間ごとに契約を更新する有期雇用契約で働く従業員です。勤務条件や福利厚生は会社によって異なりますが、基本的に社会保険や雇用保険には加入します。契約期間が有期である点以外は正社員と近いケースも多く、業務内容によっては正社員同様の責任を担います。
アルバイト・パート
アルバイトやパートも会社と直接雇用契約を結んでいるため、従業員に該当します。勤務日数や時間が少ないことが一般的ですが、一定の労働時間を超える場合は社会保険や雇用保険に加入が必要になります。たとえば、週20時間以上勤務するアルバイトは雇用保険の対象になります。
出向元と雇用契約を結んだ出向社員
出向元企業と雇用契約を維持したまま、別の企業で勤務する出向社員も、出向元企業の従業員に含まれます。給与の支払いや社会保険の手続きは原則として出向元が行います。
従業員に含まれないケース
続いて、従業員に該当しない雇用形態や立場の人について解説します。
役員
会社の取締役や監査役などの役員は、会社法上の「役員」であり、「従業員」には含まれません。役員は会社の経営方針を決定・監督する立場であるため、労働者としての法律的保護(労働基準法の適用など)はありません。
業務委託
業務委託契約を結んで働く人は、会社と雇用契約を結んでいないため、従業員ではありません。業務の成果に対して報酬を支払う契約形態であり、社会保険や雇用保険の対象にもなりません。たとえば、外注先やビジネスパートナーなどのフリーランスや個人事業主がこれに該当します。
派遣社員
派遣社員は、派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先で業務を行います。このため、派遣先企業の従業員には該当しません。派遣先で勤務していても、労務管理や社会保険の手続きは派遣元が行います。
出向先企業と雇用契約を結んだ出向社員
出向先企業と新たに雇用契約を結んだ場合、その出向社員は出向先企業の従業員となります。出向元との雇用関係は終了しているため、従業員としてカウントする場合は出向先企業で計上することになります。
「従業員数」は正社員以外の契約社員やアルバイトも含む
ここからは、従業員数の数え方について解説します。従業員数は企業の規模や保険の適用、助成金申請などで必要になるため、正確に把握することが大切です。
従業員数には、正社員だけでなく契約社員、出向社員、アルバイト、パートも含まれます。出向社員については前述の通り、雇用契約を結んでいる企業でカウントします。
「連結」と「単体(単独)」の違い
企業規模を示す際によく使われるのが、「連結」と「単体」です。
「連結」は、親会社とすべての子会社を合わせた従業員数です。グループ全体の規模感を示すときに使われます。
一方、「単体(単独)」は親会社だけの従業員数です。採用活動や助成金申請の場面では、単体の従業員数が求められることが多いため注意しましょう。
従業員が加入する保険
最後に、従業員が加入する必要のある主な保険について解説します。特にアルバイトなど短時間労働者でも、一定の条件を満たせば加入が必要になる点に留意しましょう。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した際や育児休業中などに給付金が支給される制度です。週20時間以上働くアルバイトやパートも対象となります。加入義務は事業主にあり、従業員からの保険料と事業主負担分が支払われます。
前述のとおり、会社の取締役や役員は、原則として被保険者とはならない点に注意です。
労働者災害補償保険
通称「労災保険」は、業務中や通勤中の事故に対して給付が行われる制度です。雇用保険とは異なり、労働時間や雇用期間についての条件はありません。たとえば、週20時間未満の短時間労働であっても、加入義務があります。
すべての労働者が対象であり、正社員はもちろん、契約社員やアルバイトも含まれます。保険料は全額事業主が負担します。
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
社会保険とは、主に「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の総称であり、従業員が安心して働くために必要な社会保障制度です。
健康保険・介護保険
健康保険は、病気やけがをした際の医療費を一部負担する制度です。従業員は原則として健康保険に加入する義務があります。加入対象は正社員だけでなく、一定の要件を満たした契約社員やアルバイトも含まれます。
具体的には、「週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上」である場合や、
- 従業員数が51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金88,000円以上
- 2か月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
という上記の条件を満たす場合、アルバイトであっても健康保険への加入が必要です。
※2024年10月の制度改正により、「従業員数51人以上の企業」へと対象範囲が拡大されました。
(出典元:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」)
介護保険は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が対象となり、要介護状態になった場合に介護サービスを受けられる制度です。(出典元:厚生労働省「介護保険制度について」)
健康保険に加入している場合、介護保険料も一緒に徴収されます。高齢化が進む中で、今後さらに重要性が増す制度です。
厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の年金だけでなく、病気やけがで障害を負った場合の「障害年金」や、加入者が亡くなった際の「遺族年金」なども給付されます。保険料は労使折半で負担し、給与に応じた金額が毎月控除されます。
厚生年金保険も同様に、アルバイトやパートでも、上記で紹介した所定の条件を満たせば加入義務が発生します。
アルバイト雇用の効率化で従業員管理をスムーズに
解説してきたとおり、「従業員」という枠組みには正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなど多様な雇用形態が含まれます。特にアルバイトは、繁忙期や急な欠員補充など柔軟な人員調整に欠かせない存在です。
しかし、アルバイトの採用活動に始まり、雇用契約の締結、勤務シフトの作成と調整、さらには給与計算や社会保険の手続きなど、採用から労務管理まで多くの業務負担が伴います。これらの作業をさらに効率化することができれば、より良い雇用環境の整備や、コンプライアンス遵守にもつながるでしょう。
そこで、Payment Technologyでは、アルバイトの採用やシフト管理、給与計算をスムーズに行えるサービス「エニジョブ」を提供しています。「エニジョブ」を導入すれば、アルバイトのスピーディーな採用やシフト調整はもちろん、給与計算や勤怠管理までまとめて効率化が可能です。「急な人員不足にすぐ対応したい」「効率的に従業員を確保したい」 そんな課題をお持ちの担当者の方は、ぜひ「エニジョブ」の導入をご検討ください。
まとめ
「従業員」の定義は広く、正社員だけでなく契約社員やアルバイト・パートも含まれます。一方、役員や業務委託、派遣社員は「従業員」には含まれない点に注意が必要です。
従業員数の数え方や保険加入の義務も雇用形態によって異なりますので、採用活動や労務管理を行う際には正確に理解しておくことが重要です。
そして、「人手不足に迅速に対応したい」「アルバイトの管理業務をもっと効率化したい」そんな悩みを抱える担当者の方には、「エニジョブ」の導入もおすすめです。従業員管理の負担を軽減し、より柔軟で効率的な採用体制を整えましょう。