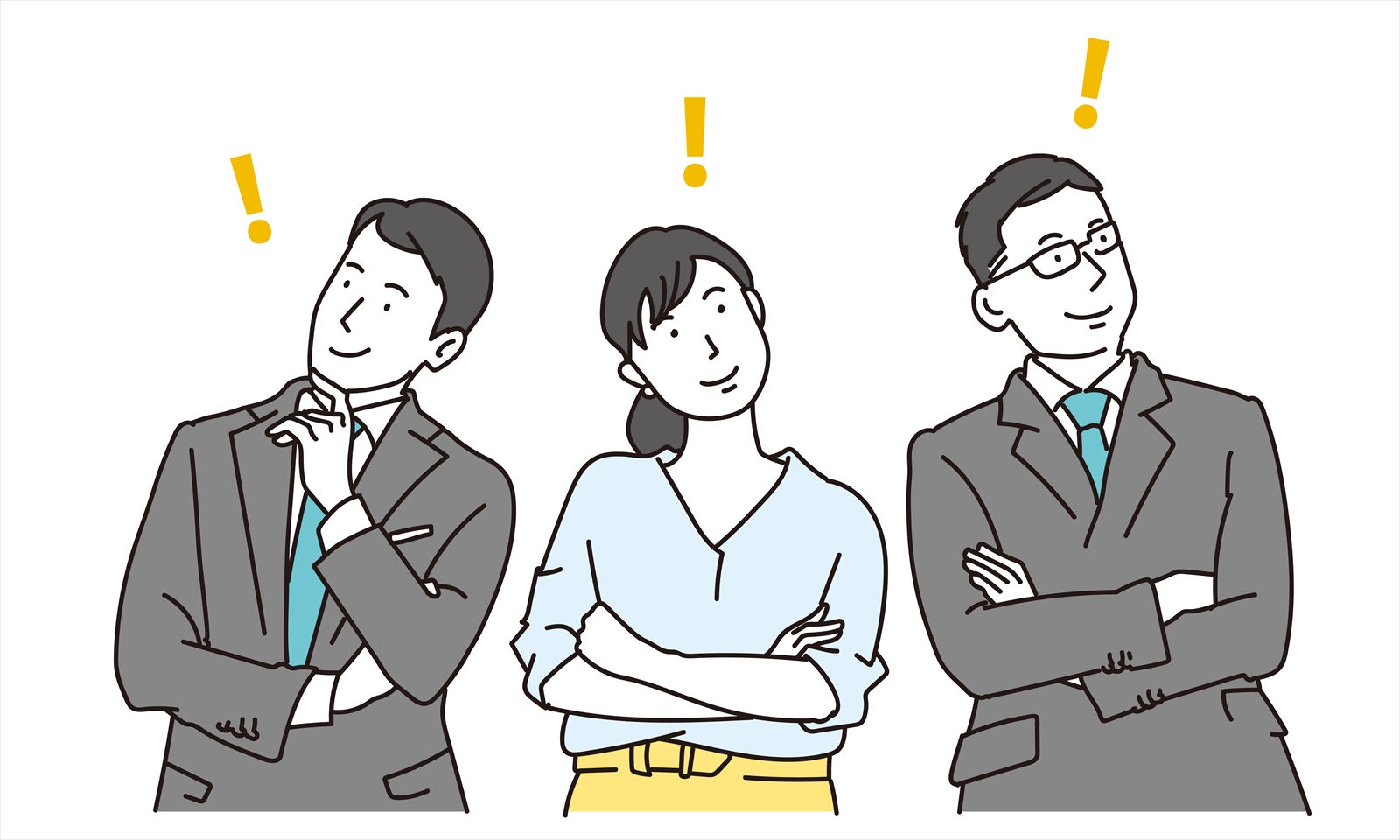アルバイト中に起こるケガや事故に備えるために知っておきたいのが労災保険の仕組みです。しかし、「アルバイトでも労災保険が適用されるのか?」「正社員と何か違いはあるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、労災保険がアルバイトにも適用される仕組み、適用の条件、労災が発生した場合の事業者の対応や申請方法、そして事業主が押さえておくべきポイントまで、分かりやすく解説します。
目次
労災保険はアルバイトにも適用される!
まずは、アルバイトにも労災保険が適用される理由と、正社員との違いについて解説します。
労災保険はすべての労働者に適用される理由
労災保険は、業務中や通勤中に起きた事故や病気に対して、医療費や休業補償などを行う制度です。この制度は、労働基準法および労働者災害補償保険法により、正社員、契約社員、パート、そしてアルバイトなど、雇用形態に関わらずすべての労働者を対象としています。
つまり、アルバイトであっても、雇用契約が成立していれば労災保険の適用対象となります。
(参考:厚生労働省「雇用・労働労災補償」)
アルバイトと正社員で違いはある?
適用範囲や給付内容に、アルバイトと正社員の間に大きな違いはありません。ただし、給付金額については「賃金額」に基づいて決まるため、アルバイトの場合は支給される金額が正社員よりも低くなることがあります。賃金額が低ければ、それに応じた補償金額となる点は押さえておくべきでしょう。
労災保険が適用されるケースとされないケース
続いて、どのような場合に労災保険が適用され、どのような場合に適用されないのか詳しく見ていきましょう。
適用されるケース【通勤途中・業務中の事故など】
労災保険が適用される代表的なケースには、勤務中に作業をしていて負傷した場合や、業務の一環で移動中に交通事故に遭った場合が含まれます。また、自宅から職場までの通勤途中で事故に巻き込まれた場合も、合理的な経路・方法で通勤していれば通勤災害として補償の対象になります。
【例】
- 飲食店で勤務中、熱い油を浴びて火傷を負った場合
- 通勤途中、駅の階段で転倒して骨折した場合
適用されないケース【勤務時間外のケガなど】
一方で、労災保険が適用されないケースもあります。たとえば、勤務終了後に私的な用事で立ち寄った先で事故に遭った場合や、勤務時間外に施設内で私的に遊んでいた際に負傷した場合、故意による自傷行為などが該当します。つまり、「業務に直接関係ない行動中のケガ」は労災保険の補償対象になりません。
【例】
- 勤務終了後に同僚と私的に飲みに行き、帰宅途中に事故に遭った場合
- 休憩時間中の買い物中に転倒してケガをした場合
(参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」)
労災保険の加入手続きは「会社」が行う
次に、アルバイトを雇用する側が行う労災保険の加入手続きと、加入漏れがもたらすリスクについて解説します。
会社が行う手続きの流れ
労災保険への加入手続きは、事業主が責任を持って行うべき義務とされています。新たに従業員(アルバイト含む)を雇った場合は、以下の流れで手続きを進めます。
- 保険関係成立届を所轄の労働基準監督署へ提出
- 概算保険料申告書を提出し、保険料を納付
(参考:厚生労働省「労働保険の加入手続きはお済みですか?」)
これにより、雇用するすべての労働者が労災保険の適用対象となります。
加入漏れが発生した場合のリスク
労災保険の加入をするよう指導があったにもかかわらず労災保険に加入していなかった場合、企業は労働保険料の徴収を受ける可能性があります。さらに、過去に遡って保険料と延滞金を支払う義務が発生し、社会的信用にも大きなダメージを与えかねません。
特にアルバイトは雇用形態が流動的なため、加入手続き漏れが起こらないよう注意が必要です。
アルバイトが労災に遭った場合の事業者の対応
ここからは、実際に労災が発生した場合の対応について見ていきましょう。まずは、アルバイトが労災事故に遭った際に、事業者が取るべき基本的な対応について説明します。
事故発生直後の対応
労災事故が発生した場合、まず最優先すべきは被災者の救護です。緊急性が高い場合は、すぐに救急車を呼び、医療機関への搬送を行います。
安全が確保できたら、警察や労働基準監督署により、現場検証や事情聴取が行われる場合があります。事故発生状況を正確に把握・記録しておきましょう。
労働者死傷病報告の提出と申請手続きのサポート
アルバイトが労災事故により死亡又は休業した場合には、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出します。
また、労災保険の申請はアルバイト本人が行うのが原則ですが、会社側も必要書類の準備や、申請に必要な証明書類の作成に協力する必要があります。詳しくは後述していますが、本人が申請手続きを円滑に行えるよう、申請方法の説明や書類の確認をサポートする体制も整えておくと安心です。
再発防止策の実施
事故発生後には、同様の事故を繰り返さないために、職場環境の改善や業務手順の見直し、安全教育の強化を行う必要があります。労災事故が起きた原因を分析し、具体的な再発防止策を講じることは、会社側の責任でもあります。
たとえば、転倒事故が起きた場合には、床面の滑り止め対策や注意喚起表示の設置を行うなど、実効性のある対策を迅速に取ることが求められます。
労災保険の申請手続き方法
次に、労災保険の申請が必要になった場合の申請方法や必要な情報、給付までの流れについてです。
申請手続きは原則「アルバイトとして働く側」が行う
労災保険の申請は、原則としてアルバイト本人が主体となって行います。ただし、会社には従業員の労災申請を助けることが法律上義務付けられており、すべての手続きをアルバイト本人だけで進めるとは限りません。実際には、会社が労災申請書類を作成し、提出手続きを代行しているケースが多いようです。
(参考:弁護士法人 咲くやこの花法律事務所 企業法務の法律相談サービス)
申請書類の作成と提出
労災保険の申請には、所定の様式で作成した「給付請求書」と「必要な添付書類」を用意します。必要書類は給付の種類ごとに異なります。また、主要様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできるため、参考にしながら準備を進めましょう。
(参考:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」)
申請書類の提出先は請求する給付の内容によって変わりますが、基本的には、所轄の労働基準監督署長あてに、労基署まで直接持って行くか、郵送で提出します。
申請後の流れと給付までの期間
申請後は労働基準監督署による調査が行われ、問題がなければ給付が決定します。給付決定までの期間は、通常1~3か月程度ですが、事故の状況や審査内容によってはさらに時間がかかる場合もあります。申請書類に不備がないよう、慎重に準備を進めることが大切です。
労災保険にはどのような補償がある?
労災保険による補償内容は多岐にわたります。ここでは、代表的な6つの給付について詳しく解説します。
療養(補償)給付
業務上または通勤途中で負傷した際、必要な治療を受けるための費用を補償する制度です。指定された医療機関を利用した場合、原則として自己負担はありません。
休業(補償)給付
労災によって働けなくなった場合、休業4日目から支給されます。支給額は、給付基礎日額の60%に、さらに特別支給金として20%が上乗せされ、実質的には約80%の収入が補償されます。
障害(補償)給付
治療が終了しても後遺障害が残った場合に支給されます。障害の程度に応じて、一時金または年金が支払われる仕組みです。
遺族(補償)給付
労災によって労働者が死亡した場合、遺族に対して年金または一時金が支給されます。遺族の範囲には、配偶者や子ども、父母などが含まれます。
傷病(補償)年金
療養を続けて1年半を経過しても症状が安定せず、障害等級に該当する場合に支給される年金です。長期療養が必要なケースで活用されます。
介護(補償)給付
労災による重度の障害により介護が必要になった場合に、介護費用を支給する制度です。
アルバイト雇用時に事業主が押さえておくべき労災管理のポイント
最後に、事業主がアルバイトを雇用する際に注意すべき労災管理のポイントをまとめます。
労災事故が起きたときの初動対応
万が一労災事故が発生した場合には、まず負傷者の救護を最優先で行いましょう。その後、速やかに社内への報告体制を整え、必要に応じて労働基準監督署にも報告します。初動対応が遅れると、損害が拡大するリスクがあります。
安全教育とマニュアル整備の重要性
事故を未然に防ぐためには、日常的な安全教育が不可欠です。アルバイトに対しても入社時研修やマニュアル配布を行い、作業手順や安全管理についてしっかりと理解させることが大切です。
労災隠しを防ぐための体制づくり
労災事故が起きたにもかかわらず、会社が報告を怠る「労災隠し」は重大な法令違反です。労働安全衛生法では厳しい罰則が定められているため、事故発生時は必ず適切な対応を取れる体制を構築しておくことが求められます。
労災保険対応を徹底し、より安心できるアルバイト雇用体制を整えよう
アルバイトにも労災保険が適用されることを理解し、適切に手続きを行うことは、事業主にとって非常に重要です。万が一の労災事故にもスムーズに対応できる体制を整えることで、アルバイトスタッフが安心して働ける環境を作り、信頼感を高めることにもつながります。
また、アルバイトの労務管理は、採用から契約手続き、シフト調整、給与計算、さらには労災対応まで、非常に多岐にわたります。特に、繁忙期の短期雇用や急な人員確保の場面では、これらを迅速かつ正確に管理する負担は少なくありません。
そのような労務管理の効率化を目指す企業には、アルバイト管理をトータルでサポートできるサービス「エニジョブ」の導入がおすすめです。「エニジョブ」は、アルバイトの採用、シフト調整、給与計算、さらには短期雇用者の再雇用機能まで備えており、煩雑な手続きや管理業務を大幅に軽減します。結果として、労災保険対応を含めた労務リスク管理もスムーズに行える体制づくりが可能です。
アルバイトの労災保険対応や管理体制をより万全に整えたいと考えている担当者の方は、ぜひ「エニジョブ」の活用をご検討ください。